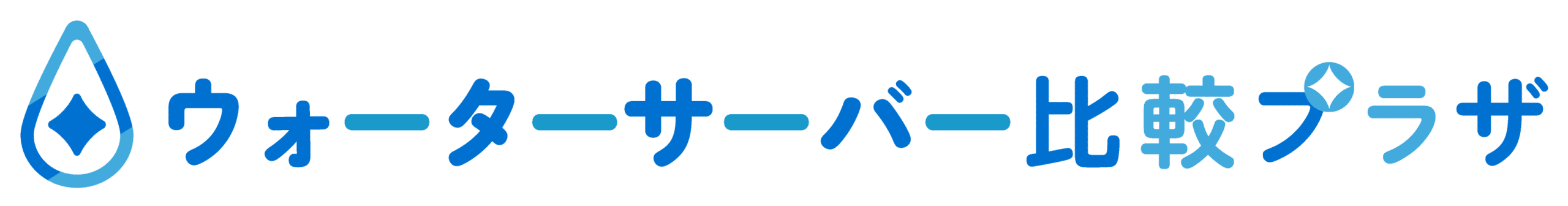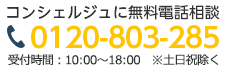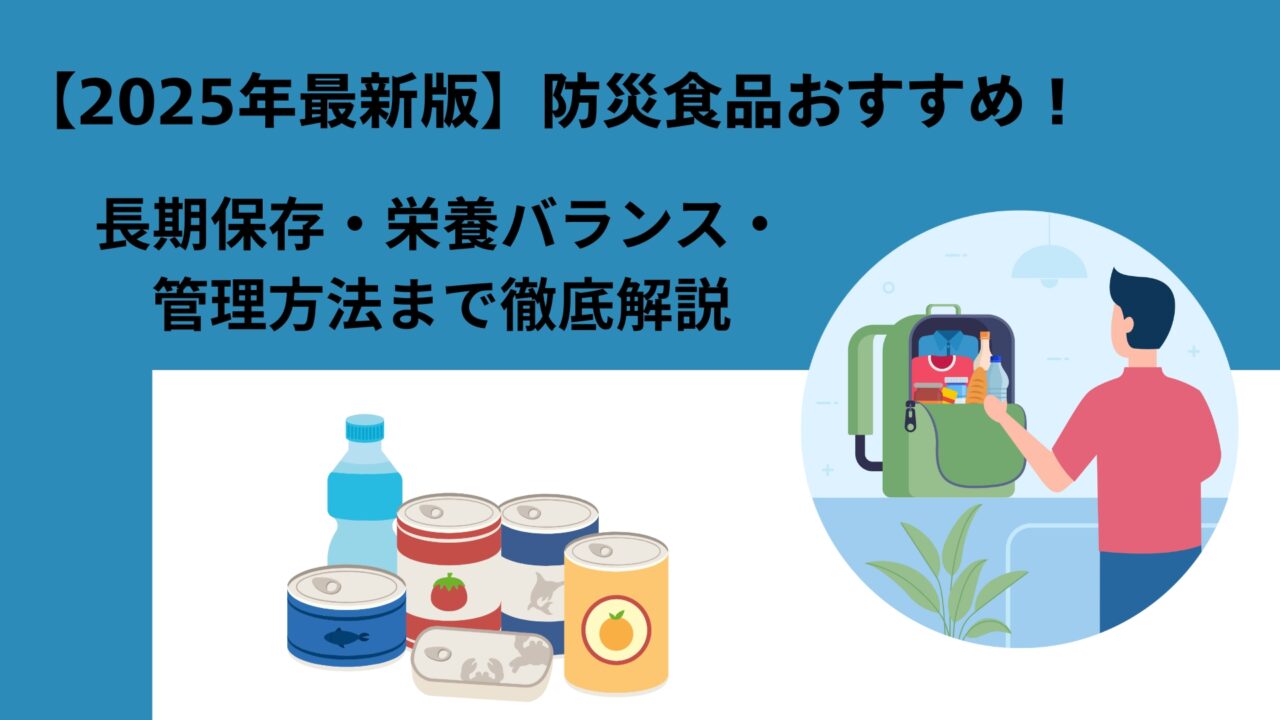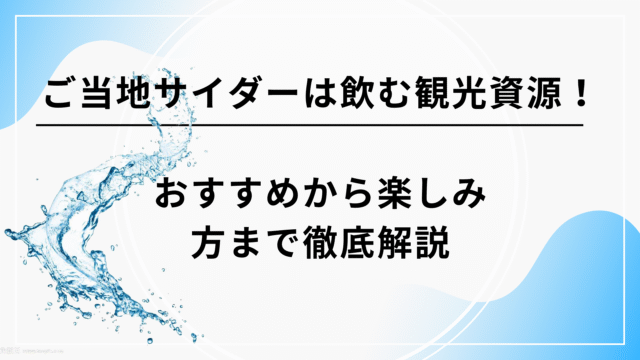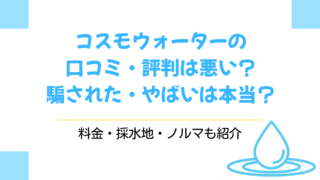災害発生時には、ライフラインの停止や物流の遅延により、食料の確保が困難になるケースがあります。
内閣府の資料でも「最低3日分、可能であれば1週間分以上の食料備蓄」が推奨されており、備蓄の質と量が生命維持に直結するのです。
本記事では、調理不要、長期保存、栄養バランスなど5つの観点から防災食品の選び方を整理し、おすすめ商品を紹介します。
また、期限管理に有効な「ローリングストック法」も解説しているため、ぜひ参考にしてください。
防災食品を備えるべき理由と必要量の目安
災害時の健康維持や生活復旧のため、防災食品の備蓄は不可欠です。
- 災害時に備蓄が必要な理由
- 人数・日数別の必要量とリスト
栄養バランスを考慮した食品選びに加え、食べ慣れた食品の備蓄が心の安定にもつながります。
災害時に備蓄が必要な理由
災害発生直後は、電気・水道・ガスなどのライフラインが停止し、物流も停止するおそれがあります。
政府は、ライフラインの復旧におおむね3日を要すると想定しています。
加えて、災害時は炭水化物中心の支援食が多く、栄養不足や健康リスクが懸念されるため、バランスの取れた食事を確保することが重要です。
人数・日数別の必要量とリスト
災害発生時は、1人あたり最低3日分、可能であれば1週間分の食料や水の備蓄が推奨されています。
目安として、水は1人1日3リットルで計9リットル、主食9食、缶詰6缶、レトルト食品6個が必要です。
加えて、乳幼児や高齢者などの災害時要配慮者については、物流の回復が遅れる可能性に備え、2週間分以上の備蓄が望ましいとされています。
家族構成や持病の有無に応じて、アレルギー対応食やベビーフード、常用薬、飲料水の量なども個別に調整する必要があります。
防災食品の5つの選び方
防災食品を選ぶ際は、「保存期間が長い食品を用意する」だけでは不十分です。
過去の大規模災害では、ライフラインの停止や物流の途絶により、食事の確保が困難になり、避難生活の長期化や栄養不足、食欲低下、持病の悪化などが問題となりました。
そのため、以下の5つの観点から食品を選定することが重要です。
- 調理不要でそのまま食べられる
- 長期保存が可能
- 食べ慣れた味・嗜好に合う
- 栄養バランスに配慮されている
- アレルギーや要配慮者に対応している
調理不要でそのまま食べられる
災害時は電気・ガス・水道などのライフラインが停止し、調理や食器洗いが困難になることが想定されています。
そのため、火や水を使わずにそのまま食べられる食品であるのが重要です。
調理不要な食品は、限られた飲料水を確保できる利点があるほか、衛生管理が難しい避難生活でも食中毒のリスクを抑えられます。
また、開封するだけで食べられる食品は、被災者の負担を軽減し、素早くエネルギーと栄養の補給が可能です。
長期保存が可能
防災食品を選ぶ際は、長期保存が可能であるかを重視する必要があります。
災害時に備蓄食品の賞味期限が切れていた場合、生命維持に必要な栄養摂取が困難になるためです。
5年以上保存できるパンやフリーズドライ食品、最長で25年保存可能な製品もあり、これらを選ぶことで頻繁な買い替えの手間を減らせます。
また、大規模災害では物流機能の復旧に時間を要するため、自力で一定期間を乗り切る備えが必要です。
近年は、短期的な支援までのつなぎではなく、長期的な避難生活を前提とした備蓄が求められています。
食べ慣れた味・嗜好に合う
災害時には環境の変化や精神的な不安から食欲が低下しやすいため、普段から食べ慣れた味や好みに合った食品を備蓄しておくことが重要です。
慣れない味や食材は拒否反応を引き起こす可能性があり、特に乳幼児や高齢者、慢性疾患を抱える人などは栄養摂取が困難になるリスクが高まります。
また、同じ食事が続くことによる飽きや満足度の低下も避けるべき課題です。
食べ慣れた食品を中心に複数のバリエーションを用意することで、精神的負担を軽減し、食事から気力や活力を維持できます。
栄養バランスに配慮されている
災害時の食事は炭水化物に偏りやすく、野菜・タンパク質・ビタミン類が不足しがちです。
実際、東日本大震災後の調査では、発災1か月後にエネルギー・たんぱく質・ビタミンの不足が指摘されています。
栄養不良は、避難所での高血圧や便秘、体調不良を引き起こす要因にもなり得ます。
長期避難生活では、栄養バランスの悪い食事が慢性疾患の悪化を招くこともあるため、レトルトおかずや野菜ジュース、魚・肉の缶詰などを組み合わせた備蓄が必要です。
アレルギーや要配慮者に対応している
災害時には、高齢者、乳幼児、妊産婦、慢性疾患患者、食物アレルギー疾患者など、食事に特別な配慮が必要な「要配慮者」への対応が不可欠です。
避難生活では運動不足やストレスに加え、栄養バランスの悪い食事が高血圧などの健康悪化を招く可能性があるため、低糖質・減塩食品やアレルギー対応食、やわらか食などの備蓄が求められます。
特にアレルギーを避けた食品は、調理時の混入リスクを防ぐため、事前に個別対応が必要です。
こうした物資は災害時に入手が困難になる傾向があるため、備蓄と周知が重要とされています。
防災食品のおすすめ商品
以下では、防災食品のおすすめ商品を3つ紹介します。
- らーめん缶(ピリ辛味噌)
- 永谷園の「フリーズドライご飯」
- ビスコ保存缶
らーめん缶(ピリ辛味噌)

業界初の小麦麺を使用した「らーめん缶」は、非常食としてもおすすめです。
麺、スープ、コーン・メンマ・ネギなどの具材がすべて入っているので、缶を開ければお湯なしですぐに食べられます。
海外輸出も可能で、動物性原料は使っておりません。
そのため冷やしても脂が固まらず、美味しくいただけます。
常温はもちろん、温めても風味豊かに楽しめる逸品です。
新登場したピリ辛味噌味は、味噌のコクにスパイシーな辛味が加わった本格派の味わいで、一度食べるとクセになるおいしさです。
また、常温で3年間の長期保存ができます。
電気やガスが使えない状況でも、開けるだけで満足の一杯が完成する、便利でおいしい商品です。
| らーめん缶(ピリ辛味噌)1ケース 24缶入り | 内容 |
|---|---|
| 価格 | 18,144円(税込)/送料無料 |
| 内容量 | 1缶 250g × 24缶 |
| 賞味期限 | 常温で3年間保存可能(缶底に記載) |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 |
| 原材料 | 米みそ(国内製造)、コーン、めん(植物性たん白・小麦粉・食塩)、メンマ、香味調味料、ネギ、にんにくペースト、ラー油、砂糖、豆板醤、おろししょうが/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酒精、かんすい、酸味料、リン酸塩(Na)、漂白剤(亜硫酸塩)※一部に小麦・大豆・ごまを含む |
| 製造者 | 株式会社三星(青森県八戸市大字白銀町字三島下92) |
| 販売者 | 株式会社丸山製麺(東京都大田区上池台5-20-13/TEL 03-3720-5522) |
| 注意事項 | 本製品の製造ラインでは、かに・えび・卵・乳成分を使用した製品も製造しています。 |
永谷園の「フリーズドライご飯」

永谷園の「フリーズドライご飯」は、約7年の長期保存が可能な非常食で、災害時の備蓄品として適しています。
フリーズドライ製法により、調理不要でそのまま食べることができ、湯や水での復元も可能です。
パウチ包装で軽量かつコンパクト、においを抑えるジッパーやスプーンの同封により使い勝手にも配慮されています。
サクサクとした食感で、常温でも摂取可能です。
調理器具不要で後片付けも簡単な設計も支持されるポイントといえます。
| 永谷園の「フリーズドライご飯」 | 内容 |
|---|---|
| 価格 | 543円〜 |
| 内容量 | 1袋 260g |
| 賞味期限 | 常温で7年間保存可能 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 |
| 原材料 | 【チャーハン味】ごはん(うるち米(国産)・植物油脂)・玉子そぼろ・食塩・ポークエキス・醤油・オイスターソース(小麦・大豆を含む)・赤ピーマン・乾燥ネギ・にんにく・植物油脂(ごまを含む)・チキンエキス・胡椒 調味料(アミノ酸等):トレハロース・酸化防止剤(ビタミンE)・カロチノイド色素、【炊き込み五目】ごはん(うるち米(国産)、植物油脂)、醤油、ごぼう、乾燥人参、食塩、昆布エキス、チキンエキス、乾燥ねぎ、生姜、椎茸、ひじき、砂糖、鰹節エキス. 【カレー味】ごはん(うるち米(国産)、植物油脂)、カレールゥ(乳成分・小麦・大豆を含む)、トマトペースト、乾燥人参、カレー粉、炒め玉ねぎ、食塩、砂糖、ポークエキス、ビーフエキス、パセリ、にんにく/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、【ピラフ味】ごはん(うるち米(国産)、植物油脂)、とうもろこし、炒め玉ねぎ、チキンエキス(小麦を含む)、食塩、コンソメ(大豆を含む)、かまぼこ(卵を含む)、貝柱エキス、砂糖、パセリ/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、加工でん粉、酸化防止剤(ビタミンE)、紅麹色素、香料、カロチノイド色素、カラメル色素 |
| 製造者 | 株式会社永谷園 東京都港区西新橋2丁目36番1号 |
ビスコ保存缶

ビスコ保存缶は、5年3ヶ月の長期保存が可能な栄養菓子で、災害時の備蓄食品として適しています。
脱酸素剤封入により密閉保存されており、開封後はそのまま食べられます。
一口サイズで口どけが良く、水分が少ない環境下でも食べやすいのが特徴です。
カルシウムやビタミンB群、D、食物繊維、乳酸菌入りクリームなどを含み、避難時に不足しがちな栄養補給に適しています。
小袋包装で管理もしやすく、子どもから高齢者まで幅広く対応が可能です。
| ビスコ保存缶 | 内容 |
|---|---|
| 価格 | 498円〜 |
| 内容量 | 30枚(5枚×6パック) |
| 賞味期限 | 常温で5年6ヶ月保存可能 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 |
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、乳糖、全粉乳、イヌリン、発酵液、食塩、でん粉、小麦たんぱく、乳酸菌/炭酸Ca、膨脹剤、香料、乳化剤、V.B1、V.B2、V.D、(一部に乳成分・小麦を含む) |
| 製造者 | 江崎グリコ株式会社(大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6番5号) |
防災食品の管理は「ローリングストック法」で解決
ローリングストック法とは、日常的に消費している食品を少し多めに備え、古いものから順に消費し、使った分を補充する備蓄手法です。
ローリングストック法を実践するには、まず一人あたり最低3日分、可能であれば1週間分以上の飲料水や食料の備蓄量を設定します。
要配慮者がいる場合は2週間分が目安です。
以下では、ローリングストック法の活用方法を紹介します。
- ローリングストック法を導入すべき理由
- 日常で取り入れるコツ
ローリングストック法を導入すべき理由
災害時の食料供給では、栄養バランスや食品の多様性が課題とされており、ローリングストック法を取り入れることで常に新しい状態の非常食を確保できます。
また、普段から食べ慣れた食品を中心に備蓄することで、災害時のストレスや食欲低下を防ぎやすくなります。
非常食専用品と比較して費用を抑えられる点や、賞味期限切れによる食品ロスの削減も大きな利点です。
さらに、カセットコンロやガスボンベなどの調理資材も合わせて備蓄すれば、被災時に温かい食事を摂取することができ、心身の安定にもつながります。
日常で取り入れるコツ
ローリングストック法を日常に取り入れるには、家族が普段食べている食品を多めに備え、古いものから順に消費し、使った分をすぐ補充する習慣を作ることが重要です。
月1回のチェック日を設け、栄養バランスを考慮しつつ主食・副食・野菜類・お菓子を組み合わせて備えると継続しやすくなります。
調理不要で常温保存でき、1回で食べ切れる食品が適しており、備蓄管理にはアプリの活用も効果的です。
生活用品にも同様の手法を応用することで、災害時への備えを強化できます。
防災食品は味・保存・栄養で選ぶのが最適
災害時に備えて防災食品を備蓄することは、健康維持や生活復旧を早めるために重要です。
最低3日分、可能であれば1週間分の食料と水を目安に用意し、特に高齢者や乳幼児など要配慮者には個別の備えが求められます。
選定時は、調理不要・長期保存・栄養バランス・アレルギー対応などに注目しましょう。
備蓄には「ローリングストック法」を活用し、日常的に消費・補充を行うことで管理負担を軽減できます。